
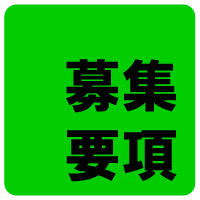
<選抜方法>
演習説明会でガイダンスする「履修希望者アンケート」に記入し、4月4日(日)午後11
時までに必着で甲宛てkinoe@i.hosei.ac.jpにメールに添付して提出する。選抜は、
提出された記述内容と面談により行う。
・4月1日
説明会(15:00からBT704)。相談会(16:00からBT702)
・4月2日
説明会(15:00からBT300)。相談会(16:00からBT300)

 |
「はじめに」に戻る | 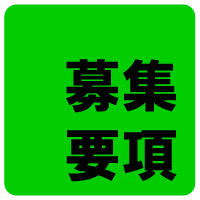 |
<選抜方法> ・4月1日 演習希望者アンケートのダウンロード |
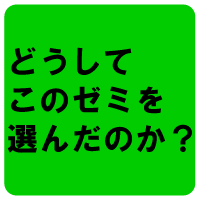
|
どうしてこのゼミを選んだのか? by 小南 陽子甲先生とは、個人的にSA前から少しだけやりとりがあって、帰国後もこちらからの要望に応えて頂いて、(ゼミ説明会とは別の時に)O崎さんも誘って一緒にお話を聞きに行きました。その際にいろいろなお話を伺って(今にして思えば、ほんのサワリ程度だったのですが)、ただ漠然と「ぐえっ、面白い」と感じたことと、直感的に「ここかなあ」と思ったことがきっかけです。つまりはよく言う「ご縁」というものだったと思います。2年間のゼミを終えた今では、良い選択をしたと思いますが、実を言うとゼミ選びの際にはっきりとした目的があったわけではありませんでした。 甲ゼミに入って2年、どうだったか?そう簡単には語れないというのが実情です。就職活動で聞かれるから、ゼミに入って何を学び取って、どんな成果を上げることができたのかとか、考えようとは、しました。・・・・・・が。結局いまだにきっちりとは話せないですねえ( ̄〜 ̄;) だけどそこを何とか、敢えて無理矢理話してみると。私が学んだことは大別して、3種類あります。
さて、私が「それ以外」のことから何を得たのかというと、
最後に挙げた知識の面では、やはり一般レベルよりも「ちょっとは知っている」レベルに過ぎないと思います。(もちろんそのレベルで留まるかどうかは、本人の努力にかかっていることは言うまでもありませんよ) だけど、この研究室の良いところは、そんな人の「感性で勝負できる」ところなんじゃないかと思います。 では次に、「自分の研究である"コミュニケーション"」の研究を通じて何を知ったのかと言うと、 細々とはあるけれど、一言で言うならこれにつきるんじゃないかと思います。私にとって、これは、ほんとに、単に「知ったこと」というよりは「痛感したこと」。まさに痛感したとしか言いようがないです。甲ゼミでは、「どんなに小さなことでも良いから、自分で新しいことを考え出して世に問う」というのがゼミ生の基本姿勢になっています。が。実は非常に大変なことであります。なかなかどうして出来ないことなのです。かくいう私も、3年生ぐらいまでは輪講などで新しい知識を得るたびに「これ、面白い。面白い。」と連呼してみたり、「この技術が今後どうなっていくのか見守りたい」としたり顔で言ってみたり、「この研究はどうかと思うねえ」なんて気軽に批判してみたりしていたのですが。それって、結局自分は何も生み出していないし、何の努力もしていない。だけど自分自身は「成長している」気分になってしまうという落とし穴があるのです。もし私が甲ゼミに入らなければ、きっとそのままいい気になって卒業していたことだと思います。 "コミュニケーション"は私にとって、ゼミに入った当初から興味のあった分野で、自分で研究してみたいと思ったから研究していたテーマです。つまり、好きでやっていたわけです。だけど、その好きなテーマに向き合うことが、こんなに苦しいのだとは思ってもみませんでした。もちろん、この苦しさというのは、何もコミュニケーションの研究に限ったことではないでしょう。きっと、どんなテーマでも、本気で取り組もうとすると苦しさが出てくるのだと思います。でも、その分、卒論を終えた後の充実感、達成感は。これはもう筆舌に表しがたいものでした。大学受験の時も終わった後に解放感があったけれど、それとはまた違うレベルの感覚を味わうことができました。きっとこれも研究の醍醐味なのでしょう。 甲ゼミに入っての2年間。得たことは、本当にたくさんありました。けれども、やはり自分の方から能動的に研究に取り組めたことが、私にとって一番の収穫だったと思います。そして、常に「この人には勝てないなあ」と思わせてくれる他のゼミ生たちに囲まれていたこと。これはもう、私の人生においての、得難い宝物かもしれませんね。 |