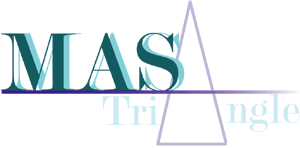
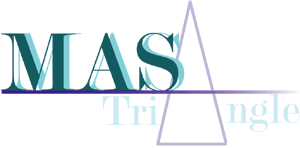 |
「音の三要素」 |
まず最初に、音とは何なのかを考えてみましょう。人間は空気の振動を音として認識します。しかし、 この世界には様々な音が溢れているのに、人間はどうやって違いを感じるのでしょうか?それぞれの 音が持つ固有の性質は、音の三要素によって定義されます。音の三要素には 音の高さ・音量・音色があります。人間が音を「違う音」として認識できるのはこの三要素の違いが あるからです。
|
まず、下の様な波形を示す音があったとします。音はある基本の波形を繰り返しますが、 その1サイクルを周期といいます。周期の逆数は周波数 といわれ、この周波数が高いほど「高い音」として認識される事になります。不思議ですねぇ。下の図 で言えば、緑の音の方がピンクの音の方よりも高い音、という風になります。もっと簡単に言って しまえば、音の高さとは1秒間に何回振動するのかに関係する、という事になります。1秒間に20回 振動する音があったとすると、それは20Hzと表されます。ちなみに、 人間の聴く事のできる周波数は20hz〜20khzだと言われています。もちろん個人差はありますが。 さらに、音階で言う「い」の音(ラ、ですね)は440hz。1オクターブで倍の周波数になるように なっているそうです。右の図の下にあるサンプル音は1kHz、つまり1秒間に1000回振動している 音と、100Hz、一秒間に100回振動している音です。聞き比べてみて下さい。 |
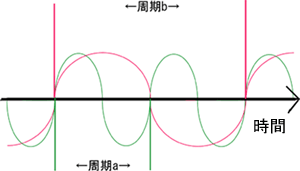
|
|
| 1kHzの音 | 100Hzの音 |
|
波形の振幅が大きい方が大きい音・・・と物理の時間に習った気がするのですが、実際に音の事を 考えてみると、音の大きさというのはかなりあいまいで、よくわからないもの・・・と私は思って います。人間の耳というのは精神的なものに左右されますし、周波数によっても聞こえ方は違います。 とりあえず振幅だけで考えてみましょう。下の図ではどちらの音も同じ周波数ですが、青い音のほうが 黄色い音よりも大きい音、という事になります。 |
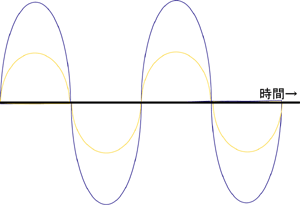
|
|
さて、右上の図に書いたような波形の音は、普段私たちが聴いている中にはあまり現われません。右上の図のような音は正弦波といいます。理科の実験室で使ったと思いますが、おんさの音がそれに近いです。でも、この世に正弦波しかなかったら、音楽の世界なんて実に味気ないですね。高さだけが違うおんさの音だけなのですから、楽器も何もあったものではない。おんさだけで演奏するようなもの。私たちが、それぞれの楽器などの音をきちんと区別して認識できるのは、音の波形の違いがあるからなのです。例えば、→ |

|
こんな感じ。音の大きさや高さはいろいろあっても、それぞれの音がぞれぞれの特徴を もっています。 |
| [TOP] | [戻る] |