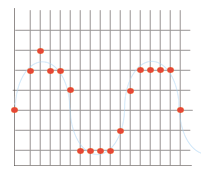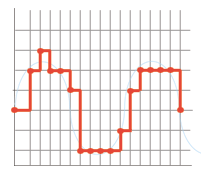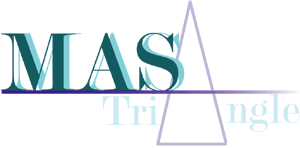
「デジタルとアナログ」
→アンケート・情報収集ページへ →次のトピックへ
デジタルにする、ということは?デジタルという言葉を聞いて、何をイメージしますか?パソコン?科学?CD?今、世の中には「デジタル」と名のつくものが溢れていますね。DVDなんかもこれからはVHSにとってかわりそうですね。私がデジタル、と聞くと、やはりCDやMDを思い出します。CDもMDも、そのデジタルの意味が実際にはわからずに、「デジタルはいい」という宣伝文句を鵜呑みにして、やたら欲しがった子供でございました。では、とりあえずそのCDやMDなんかの基礎となる、「音をデジタルにする」事について考えてみます。
デジタルとは
まず、デジタルという言葉の定義はどうなっているのでしょう?
- ディジタル。(大辞林第二版より)・・・
- 物質・システムなどの状態を、離散的な数字・文字などの信号によって表現すること
何だか言葉だとよく分かりませんが、難しく考えなくても、私たちはデジタルをよく使っていますね。アナログ、という量は連続する量、つまり、途中ではきれないものです。机の長さを計りたい!という時に、私たちはcmなどの単位を使いますが、実際には10.3617599284・・・・cm、という風に、細かくしようとすればいくらでもできるはずなんです。でもそこまで計れないですよねそんなものさし、ないですしね。そこで、適当な単位で区切って四捨五入してしまいます。ものすごく簡単に言えばそれがデジタルにするという作業(・・・と言い切るのは乱暴かな。)。10cmでいいんです。
標本化(サンプリング)
では、改めて音をデジタルにする場合。音が波であり、一定の波形を繰り返している事は他のコンテンツでお話しています。例えば下のような波形があったとしましょう。

まず先程の話の中であったようにこの波を「一定の時間ごとに区切る」という作業をします。例えば1/100秒感覚でその時の波形の値がどうなっているかを調べるのです。これを標本化(サンプリング)といいます。その様子は以下のようになります。縦線と縦線の間が1/100秒だと思ってください。ちなみにサンプリングの周期の逆数はサンプリング周波数と呼ばれ、単位はHzで表します。この場合、サンプリング周波数は100Hzになります。CDの場合、サンプリング周波数は44.1kHzになります。
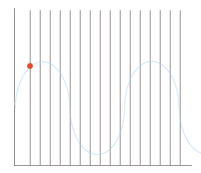
量子化
では、サンプリングする時点でその値はどうやって定めればいいのでしょう。サンプリングをして値を出すときに四捨五入をしなければなりません。その、値を定めることを量子化といい、量子化するのに何ビット使うか、というのを量子化ビット数といいます。例えば、この量子化ビット数が1だったらどうなるでしょう?使える桁は一桁、つまり1か0という値しかありません。つまり、二種類の差しか表せない事になります。この量子化ビット数、CDでは16ビットあり、なんと65536種類もの違いを表せます。こうして一定の時間ごとに値をとります。図では少しいびつになっていますが、このサンプリング周波数をもっと大きくしていけば、アナログのなめらかな波形を再現する事も可能になります。