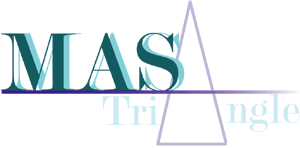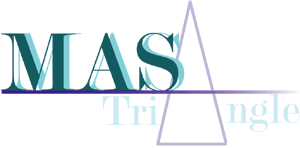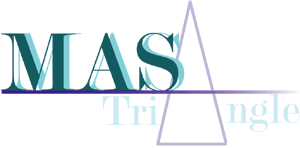 |
「音階とは」 |
音の三要素のところに、音の高さ、というものがありました。音階、というのはその音の
高さを、音楽的に一定間隔で下から上へ並べたものの事です。一言に音階、といってもそれは
「ドレミファドラシド」の事だけを指しているわけではなく、いくつかの種類があります。
昔はもともとの文化によって、それぞれの音階を持っていたわけです。
12平均律音階
|
1オクターブの間の周波数を一定にして、12分割した音階は12平均律音階、と呼ばれ、
一番私たちのなじみのある「ドレミファソラシド」はこれにあたります。1オクターブの
音(低いドと高いド)の周波数の比は1:2になっています。音楽で通常基準になるのは
A(ハ長調のラ)の音で440Hz、その1オクターブ高いAの音なら880Hzです。
|
---音階図掲載予定--- |
日本の音階
|
現在、日本の音楽シーンでヒットしているような音楽は、ほとんど上の12平均律音階の
音を使って作られています。しかし、日本には昔から独自の音階があったのです。それは大きく分けて
3つあります。
まず、陽音階。右図のような音階ですが、民謡なんかで使われるのがこの音階。
二つ目は陰音階。上がっていくときと降りてくるときに少し音が変わります。とても日本らしい
音階で、「さくらさくら」などはこの音階で作られています。
最後に沖縄の音階。はいさいおじさん!
|
---音階図掲載予定--- |